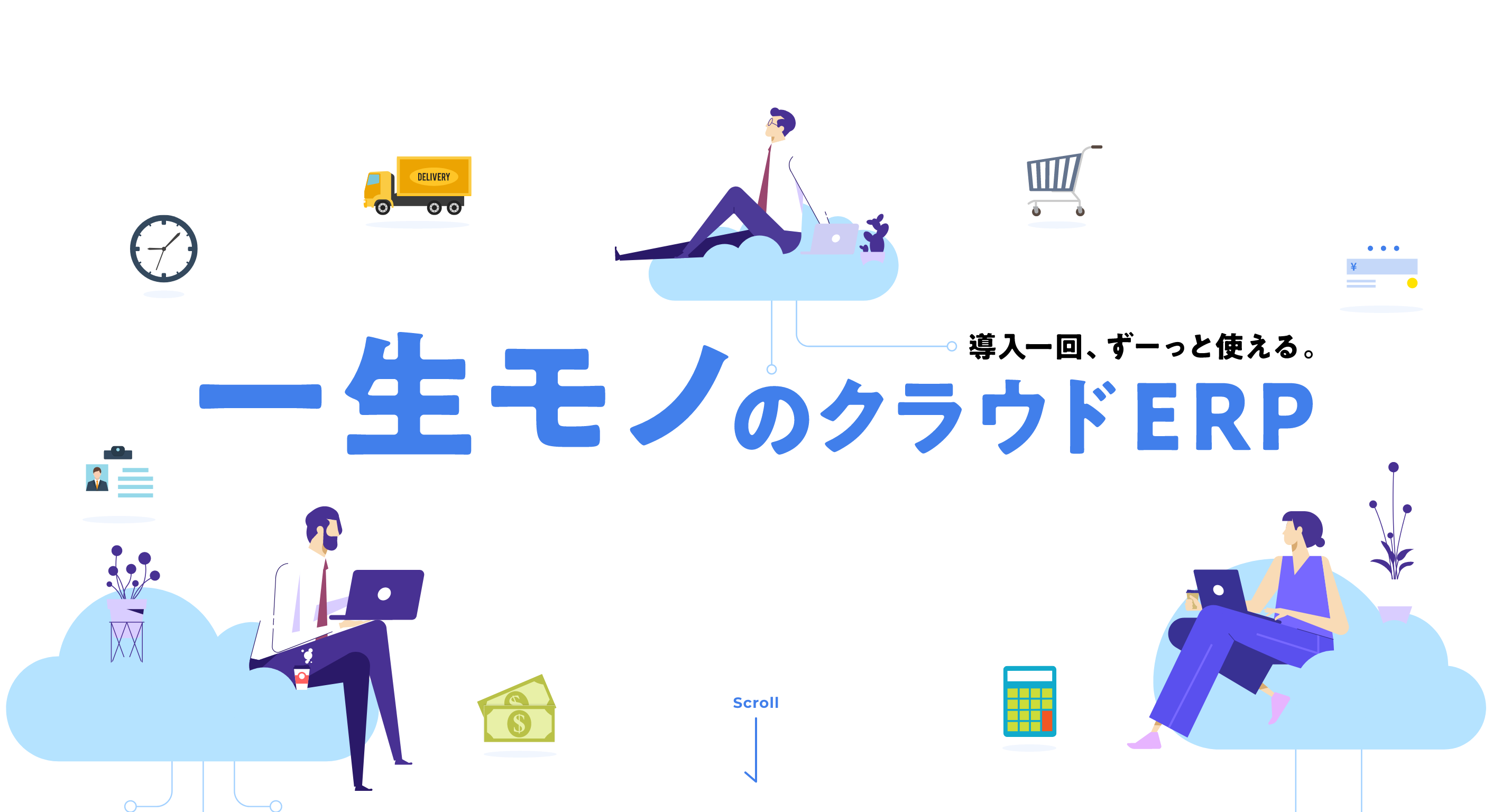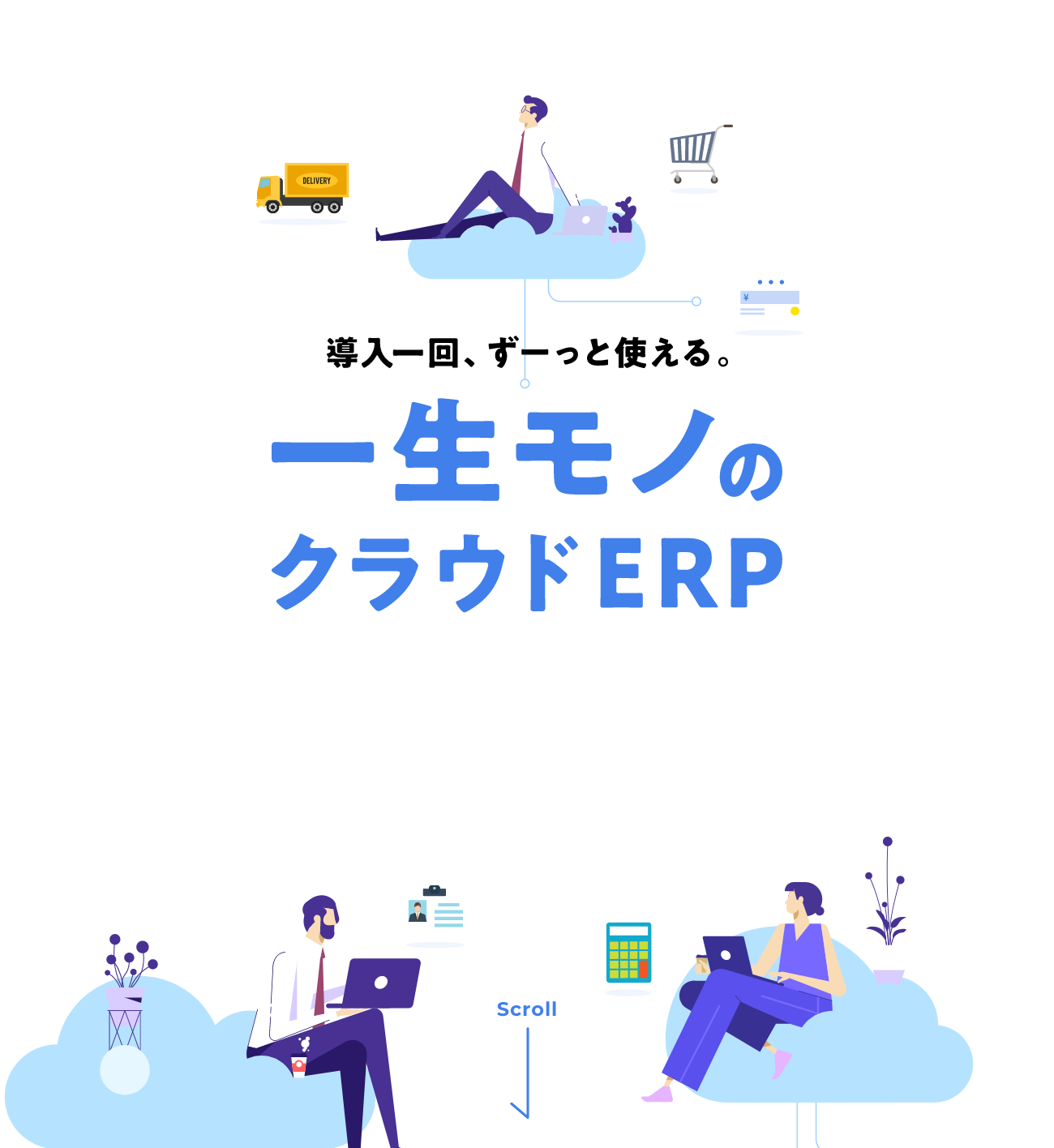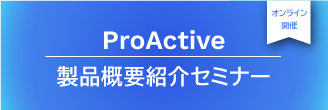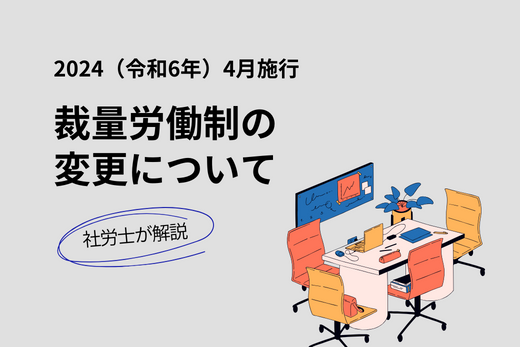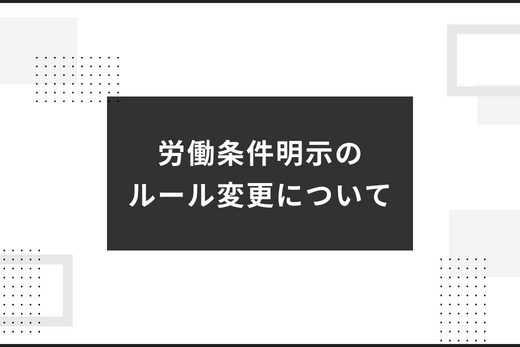About
ProActive C4とは
ProActiveは、国産初のERPとして、31年間、6,600社、300の企業グループを超える導入実績を持つSCSKのERPパッケージです。
ProActiveの新シリーズとなる、「ProActive C4」は、これまで多数のERP導入実績で培ってきた業務プロセスのノウハウとSCSKグループの総合力を活かし、お客様の成長を支援します。
-
安全性や信頼性に
優れたクラウドERP -
日々の使いやすさに
こだわったUI・UX -
ビジネス環境の変化に
素早く対応するスマート導入 -
長期にわたり安心して
使い続けられるスマート保守 -
システムからオペレーションまで
一貫して提供するBPOサービス
Module
ProActiveの対応業務
ProActiveは、会計、人事給与、販売管理、経費、勤怠管理まで、基幹業務全般をカバーします。
また、必要な業務システムからの段階的導入やグループ展開も可能です。
-

Accounting
会計
経理DXの推進に向け、経理業務のデジタル化、ペーパーレス化などを推進します。また、法改正や会計制度の変更など、経理部門の抱える課題を解決します。
-

Human Resource
人事・給与
人事の定型・非定型業務の業務効率を改善し、給与業務のデジタル化の促進により、人事DXの推進や人事戦略の立案など、戦略的な業務へのシフトを実現します。
-

Sales Distribution
販売管理
国内の販売・購買業務から請求・回収・支払の管理業務、そして貿易取引までを一元管理。世界を舞台に戦う日本企業を支援します。
-

Expense / Attendance
経費・勤怠管理
スマートフォンで行う経費申請・精算と、多様な勤務形態・雇用契約に対応した勤怠管理により、場所を選ばない、柔軟な働き方の実現を支援します。
Solution by Purpose
目的別ソリューション

Column
お役立ちコラム
ERPをはじめとするIT関連のトレンドや、法改正・制度改正などのトピックスを定期的にお届けしております。
Case study
導入事例
6,600社、300の企業グループを超えるお客様にご利用いただいています。

News
新着情報
-
2024.04.16トピックス
株式会社毎日新聞社様の導入事例を公開しました
-
2024.03.29トピックス
SONY×データビークル×SCSK 3社共催セミナーを開催いたします(4/24)
-
2024.03.28トピックス
IBM ソリューション ブログに、ProActiveに関する記事が掲載されました
『レガシーシステムと共に変革を目指す – 長年お使いの基幹システムの効果的な刷新のアプローチとは –』 -
2024.02.27ニュース
SCSKのERP「ProActive」 、Amazon QuickSightと連携し
中堅企業のデータドリブン経営を支援する「ダッシュボードソリューション」を提供開始 -
2024.02.01トピックス
グリーンスタンプ株式会社様の導入事例を公開しました