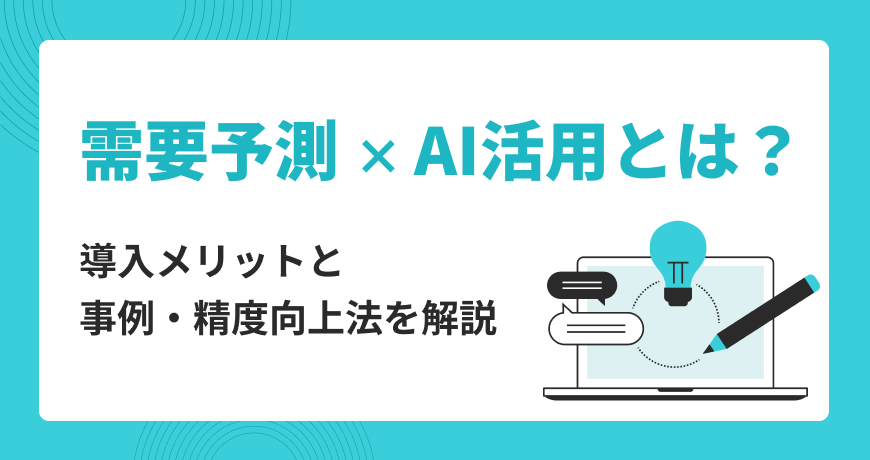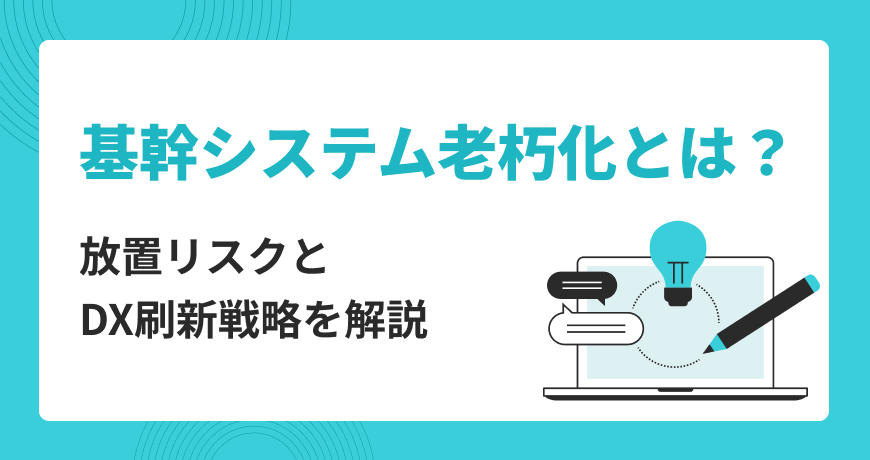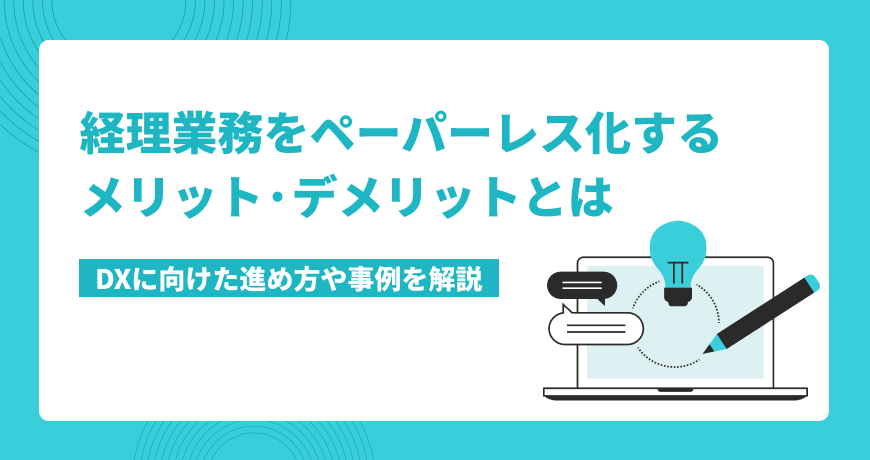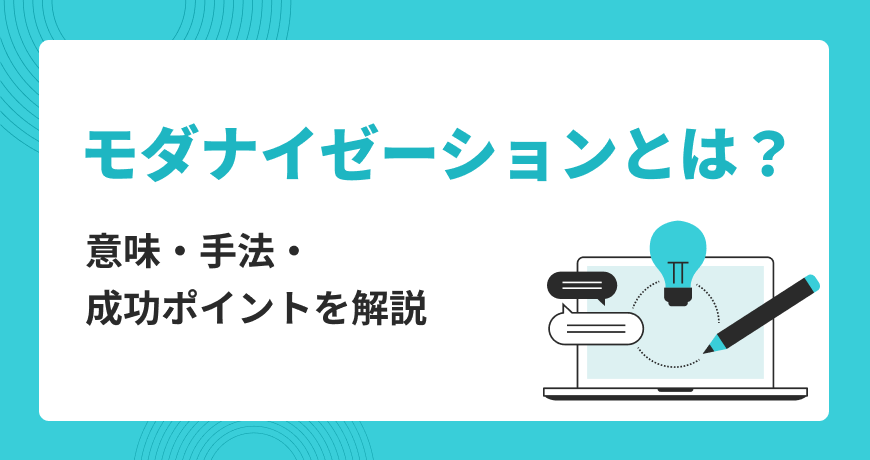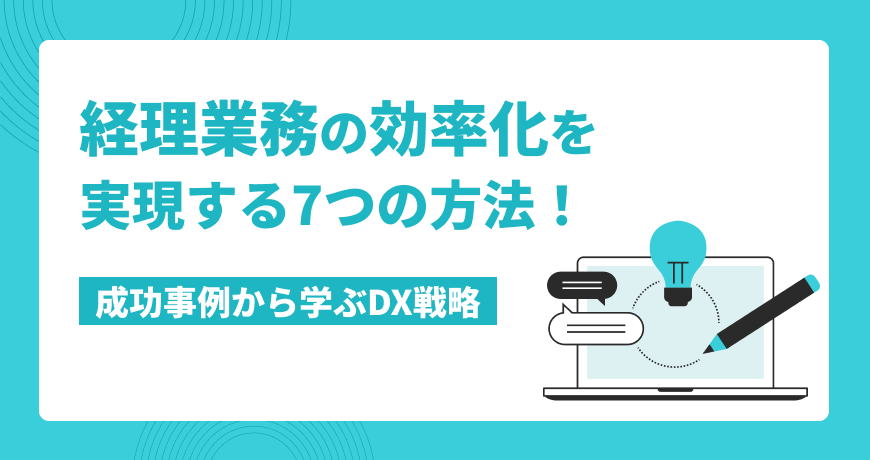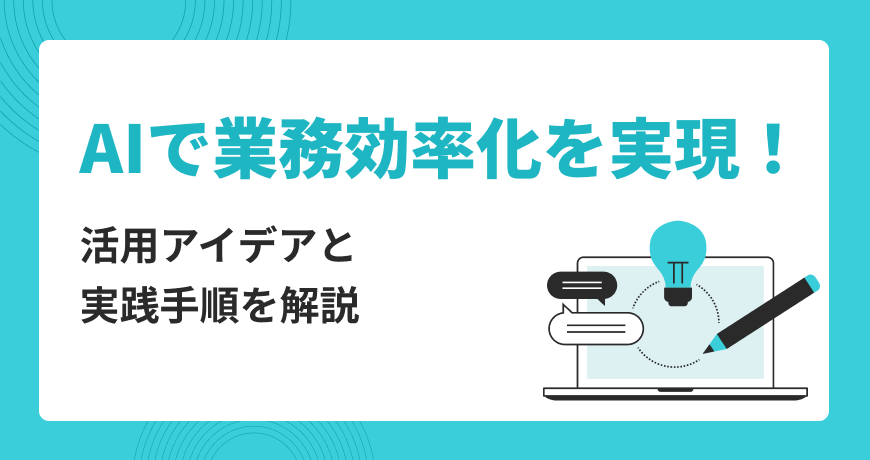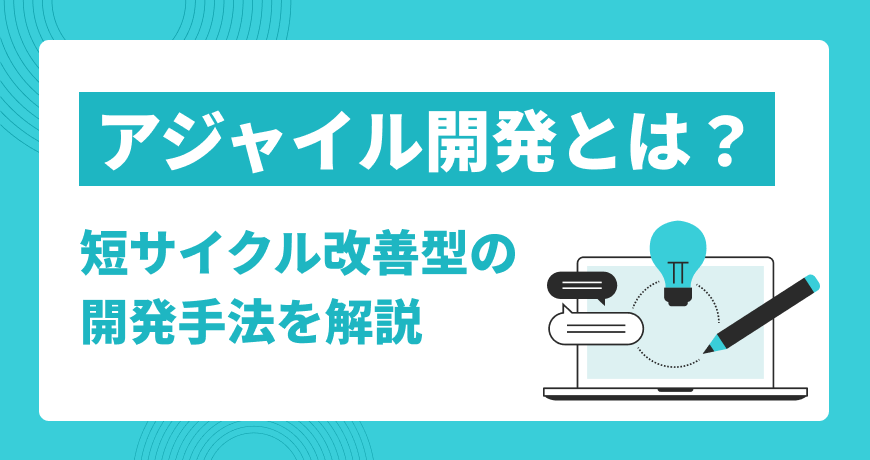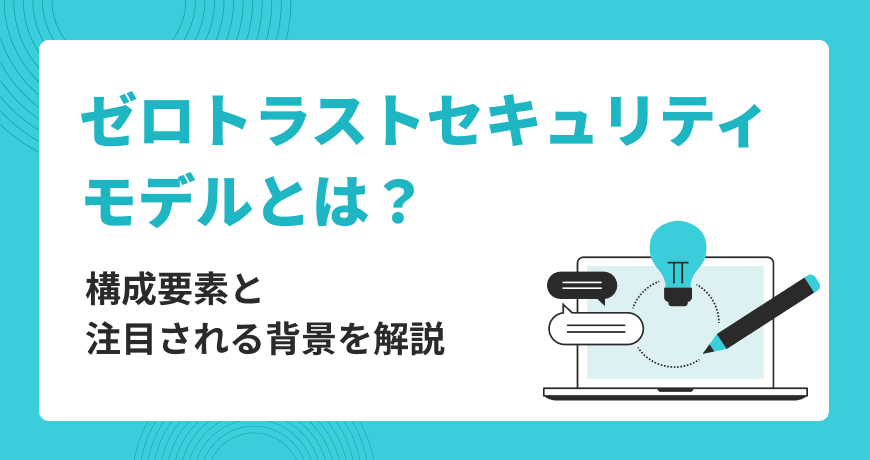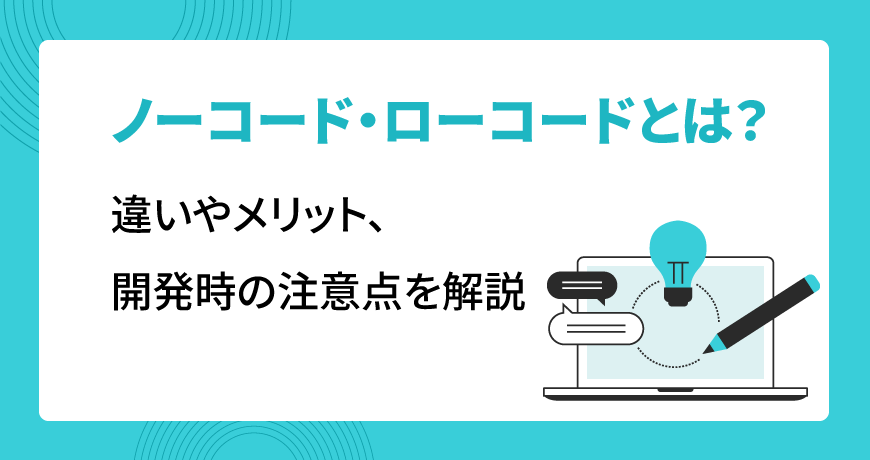
アプリケーションやシステム開発のニーズが高まる一方で、多くの企業が人材不足や開発コストの増大といった課題に直面しています。こうした状況の中で注目を集めているのが、「ノーコード」や「ローコード」といった新たな開発アプローチです。専門的なプログラミングスキルを持たない社員でも開発に携わることができるため、開発期間の短縮や業務の効率化が図れるだけでなく、企業の競争力強化にも貢献します。
この記事では、ノーコードとローコードの違いやメリット、開発時に注意すべきポイントについて詳しく解説します。
目次
ノーコード・ローコードとは
ノーコード・ローコードとは、従来のプログラミング知識を必要とせず、視覚的な操作や簡単な設定でアプリケーションやシステムを開発できる技術・ツールです。ドラッグ&ドロップやテンプレートを活用することで、Webサイトや業務システムを効率的に構築できます。ノーコードとローコードの違いは以下の通りです。
| ノーコード |
|
|---|---|
| ローコード |
|
どちらを選ぶべきかは、開発するシステムの規模や複雑さ、必要な機能、開発者のスキルレベルによって異なります。シンプルな機能であればノーコードを、より柔軟性や拡張性を求める場合はローコードが向いています。これらのツールを活用することで、アイデアから実装までの期間を大幅に短縮し、開発のハードルを下げることが可能です。
ノーコードとローコードの違い
ノーコードとローコードの違いは、次の表のとおりです。
| ノーコード | ローコード | |
|---|---|---|
| プログラミング知識 | 不要(あれば有利) | 基礎知識が必要 |
| 向いている開発 | シンプルなアプリケーション | 複雑なシステム開発 |
| カスタマイズ性 | 限定的 | 高い柔軟性 |
| 開発スピード | 非常に高速 | 高速(従来開発比) |
ノーコードは、コードを一切記述せずに開発できるため、プログラミング未経験者でもアプリケーションやシステムを構築可能です。ツールによってはテンプレートベースの開発もでき、迅速なプロトタイプ作成や基本的な業務システムの構築に適しています。
ローコードは、最小限のコーディング知識を活用することで、ノーコードでは実現困難な高度なカスタマイズや複雑なビジネスロジックを実装できます。既存システムとの連携や、拡張性の高いシステムの開発が可能です。
本章では、それぞれの開発手法の特徴や活用方法について詳しく解説します。
ノーコード開発
ノーコード開発は、プログラミングの知識を必要とせず、視覚的な操作のみでアプリケーションやシステムを開発できる手法です。主な特徴は次のとおりです。
| プログラミング知識の必要性 |
|
|---|---|
| 操作の直感性 |
|
| 開発の柔軟性 |
|
ローコード開発
ローコード開発とは、基本機能は視覚的操作で開発し、高度な機能やカスタマイズのために最小限のコード記述を行う開発手法です。
ローコード開発の主な特徴は次のとおりです。
| プログラミング知識の必要性 |
|
|---|---|
| 柔軟性と複雑なシステムへの対応 |
|
| 開発の柔軟性 |
|
ノーコード・ローコード開発のメリット
ノーコード・ローコードによる開発のメリットを3つ紹介します。
- ・ IT人材不足の解消に繋がる
- ・ 開発スピードが向上する
- ・ 開発コストを低減できる
IT人材不足の解消に繋がる
深刻化するIT人材不足の解決策として、ノーコード・ローコード開発が注目されています。最大の特徴は、プログラミング経験のない業務部門の社員でも、システム開発に直接参加できることです。
これまでシステム開発は専門のIT人材に依存していました。しかし、ノーコード・ローコードツールを使えば、業務部門の社員が現場のニーズを直接システムに反映できるようになります。顧客管理ツールや申請ワークフローなど、自部門の業務に最適化されたシステムを自ら構築することで、IT部門のリソースをより戦略的な開発に集中させることが可能です。
この取り組みは単なる人材不足の解消にとどまらず、組織全体のデジタルリテラシー向上という副次的効果も生み出します。
開発スピードが向上する
ノーコード・ローコードは、開発スピードの向上に役立ちます。
ノーコード・ローコード開発では、プログラミングコードを記述する手間がほとんど不要なため、開発にかかる時間を大幅に短縮できます。たとえば、従来であれば数週間から数ヶ月かかっていたシステム開発も、数日あるいは数時間で完了することが可能です。
特に、短期間でのプロトタイプ作成に非常に有効です。アイデアをすぐに形にして試せるため、市場の変化や顧客ニーズへの迅速な対応がしやすくなります。また、プロトタイプを基に改善を重ねることで、より最適なシステムを効率的に開発できます。
ノーコード・ローコード開発は、変化の激しい現代においてビジネスの機会を逃さず、競争優位性を築くための重要な手段と言えるでしょう。
開発コストを低減できる
ノーコード・ローコード開発は、システム開発にかかるコストを大幅に削減する効果があります。なぜなら、専門のプログラマーを必要とする機会が少なくなるからです。ノーコード・ローコード開発では、プログラミングの知識がなくてもシステムを開発できるため、高額な人件費がかかる専門人材への依存度を低減できます。
さらに、開発にかかる期間を大幅に短縮できる点も、コスト削減につながります。従来の開発手法に比べて開発スピードが速いため、人件費やインフラコストなど、開発期間中に発生する費用を抑えることが可能です。早期にシステムをリリースできることで、ビジネスチャンスを最大限に活かせるようになります。
このように、ノーコード・ローコード開発は、人件費と開発期間の両面でコスト削減を実現し、より手軽にシステム開発を行うことを可能にします。
ノーコード・ローコード開発時の注意点
ノーコード・ローコード開発時の注意点は、主に4つあります。
- ・ シャドーITやセキュリティリスクがある
- ・ 高度で複雑な要件への対応に限界がある
- ・ プラットフォームに依存し過ぎない
- ・ 基本的なITリテラシーは必要になる
これらの注意点を考慮してノーコード・ローコード開発をすることで、不正アクセスや情報漏洩などのリスクを低減できるようになります。
シャドーITやセキュリティリスクがある
ノーコード・ローコード開発は、手軽にシステム開発ができる一方で、シャドーITやセキュリティリスクに十分注意しなければなりません。
【シャドーITとは】
企業の情報システム部門が把握・管理していないIT機器やサービスの利用を指します。ノーコード・ローコードプラットフォームは、開発の敷居が低いため、企業の正式承認を得ずに機密データや重要な業務プロセスを含むシステムを開発しないよう、注意が必要です。
シャドーITにより、管理者の把握していないシステムやアプリケーションが作られてしまうと、次のようなセキュリティリスクが発生するおそれがあります。
| 情報漏洩 | 管理体制が不十分なシステムに機密情報が保存されることで、データ漏洩のリスクが高まる |
|---|---|
| 不正アクセス | セキュリティ対策が不十分なシステムが攻撃の対象となり、企業全体のセキュリティが脅かされる可能性がある |
| システム障害 | 管理されていないシステムの不具合が、業務システム全体に波及するリスクがある |
これらのリスクを回避するためには、企業レベルでのノーコード・ローコードツールの利用ルール・ガイドラインを明確にし、情報システム部門が適切な管理を行う必要があります。また、社員へのセキュリティ教育も徹底し、リスク意識を高めることが重要です。
また、ノーコード・ローコードツールを選ぶ際には、多要素認証やIPアドレス制限、データ暗号化などの機能が自社のセキュリティポリシーに沿うかどうかの確認が重要です。
高度で複雑な要件への対応に限界がある
ノーコード・ローコード開発は、その手軽さとスピードが魅力です。一方で、技術的な制約により、高度で複雑な要件に対応するには限界があることを理解しておく必要があります。
ノーコード・ローコード開発は、基本的に用意されたテンプレートを組み合わせることでシステムを構築します。そのため、高度なカスタマイズや複雑な業務プロセス、特殊な処理が必要な場合、既存の機能では対応しきれないことがあります。たとえば、特定のデータベースとの連携や複雑なアルゴリズムを実装する必要がある場合、ノーコードやローコードでは対応が難しいのが現状です。
また、独自のUI/UXデザインを追求したい場合や、細かい部分まで調整が必要な場合にも、ノーコード・ローコードでは実現できないことがあります。あくまで、プラットフォームが提供する範囲内で開発することになるため、より高度で複雑なシステムを構築するには不向きです。
システム開発を検討する際には、業務・システム要件の複雑さとノーコード・ローコードの対応可能範囲を事前に評価し、適切な開発手法を選択しましょう。また、従来の業務をそのままシステム化するのではなく、ツールの特性に合わせた業務プロセスの見直しも効果的なアプローチです。
プラットフォームに依存し過ぎない
ノーコード・ローコード開発は便利な反面、プラットフォーム依存のリスクがあることを理解したうえで適切に利用しましょう。特定のプラットフォームに依存しすぎると、次のような問題が生じるおそれがあります。
| ベンダーロックインのリスク | 特定のプラットフォームに深く依存すると、サービス終了、大幅な価格改定、仕様変更などの際に、システム利用継続や移行に影響がでることがある |
|---|---|
| 乗り換えコストの発生 | プラットフォーム固有の仕様やデータ形式により、他システムへの移行時に想像以上の時間やコストがかかることがある |
| 機能制限 | プラットフォームの機能制限により、事業成長に伴う新たな要件に対応できなくなる可能性がある。特に、従来開発と比較し、システム統合やAPI連携において制約が多くなる場合がある |
これらのリスクを回避するためには、プラットフォームを選択する際に、将来の拡張性や柔軟性を考慮する必要があります。また、特定のプラットフォームに依存しすぎないように、複数のプラットフォームの比較検討や将来的な移行計画を立てておくことも重要です。
基本的なITリテラシーは必要になる
システム開発を成功させるためには、最低限のITリテラシーが必要になります。それは、ノーコード・ローコード開発時も同様です。
具体的には、次のようなITリテラシーが求められます。
| ビジネスロジックの理解 | 業務プロセスをシステムに落とし込むためには、業務の流れやルールを正確に理解する必要がある。特に例外処理や承認フロー、条件分岐を適切に設計できなければ、実用的なシステムにならないため、注意が必要 |
|---|---|
| データ設計の基礎知識 | データの適切な構造化や関連付けを理解していないと、システムを開発しても意図通りに機能しないことがある。リレーショナルデータベースの基本概念や正規化の考え方を理解することで、拡張性・保守性の高いシステム設計が可能になる |
| セキュリティに関する知識 | システムを安全に運用するためには、基本的なセキュリティ対策を理解しなければならない。アクセス権限管理、データ暗号化、個人情報保護など、包括的な理解が必要 |
| ツールに関する知識 | ノーコード・ローコードツールを使いこなすためには、ツールの操作方法を学ぶ必要がある。また、既存システムとの連携やデータ移行を行う際には、APIの基本的な仕組やデータ形式への理解が必要 |
ITリテラシーが不足していると、システムがうまく機能しない、意図しないセキュリティリスクを招くなどのさまざまなリスクが生じるおそれがあります。そのため、ノーコード・ローコード開発を効果的に活用するためには、ツールの使い方のほかに基本的なITリテラシーを身につけることが重要です。
ノーコード・ローコード開発によるカスタマイズ実施のポイント
ノーコード・ローコード開発を行うときのポイントを3つ紹介します。
- ・ 利用目的や対象業務の範囲を明確にする
- ・ 用途に適したツールを選定する
- ・ 段階的に開発を進める
それぞれのポイントを理解し、ノーコード・ローコード開発を適切に行いましょう。
利用目的や対象業務の範囲を明確にする
ノーコード・ローコード開発におけるカスタマイズを成功させるためには、はじめに利用目的と対象業務の範囲を明確にすることが重要です。
たとえば、次のようなことが挙げられます。
解決したい課題や実現したい成果を具体化する
プロジェクトの目的を明確にし、どのような問題を解決したいのか、またはどのような成果を達成したいのかを具体的に示します。たとえば、「顧客管理を効率化し、営業担当者の作業時間を〇%削減する」「申請承認プロセスの自動化により処理時間を従来の3日から1日以内に短縮する」など、定量的な数値目標を定めるのが効果的です。
対象業務やデータフローを分析し、適用可能かを判断する
対象となる業務やデータフローを詳細に分析し、ノーコード・ローコード開発が適用できるか判断します。現場担当者へのヒアリングを通じて、表面的な業務フローだけでなく、実際の運用における課題や要望を収集し、ニーズに合ったシステムを検討することが重要です。
複雑な業務や高度なカスタマイズが必要な場合は、従来のプログラミング開発との比較検討も必要です。
小規模プロジェクトやプロトタイプ開発に適しているかを検討する
対象となる業務やプロセスが、小規模なプロジェクトやプロトタイプ開発に適しているか検討します。ノーコード・ローコード開発は小規模プロジェクトやプロトタイプ開発に適したシステムです。そのため、プロジェクトが大がかりなものになる場合は、本格的なプログラミングによる手法を用いた開発が向いている場合もあります。
用途に適したツールを選定する
ノーコード・ローコード開発において用途に適したツールを選定する際には、次のポイントを考慮することが重要です。これらのポイントを踏まえることで、自社のニーズに最適なノーコード・ローコードツールを選定し、業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進することが可能になります。
必要な機能やシステム・データの連携機能を備えたツールを選ぶ
ツールが提供する機能が、自社の業務ニーズやプロジェクト要件に合致しているか確認します。特に、他のシステムとの連携が必要な場合は、APIやプラグインによるシステム・データの連携機能が充実しているかも重要です。
チームのスキルセットやITリテラシーに合ったツールを採用する
ツールの使いやすさは、チームメンバーの技術的なスキルやITリテラシーによって大きく影響されます。ノーコードツールは一般的に直感的で使いやすい傾向にありますが、ローコードツールはある程度のプログラミング知識が求められることがあります。チームがいかに早く新しいツールを習得できるかも考慮しましょう。
プラットフォームのサポートやコミュニティの充実度を確認する
ツール導入後のサポート体制やコミュニティの充実度も重要です。問題が発生した際に迅速に解決できるサポートがあるか、また他のユーザーとの情報交換ができるコミュニティが存在の存在や、技術情報の豊富さも確認します。これらにより、導入後も安心して運用できる環境が整います。
段階的に開発を進める
大規模なシステム構築の一括構築は、運用開始後に重大な不具合やユーザーニーズとの不一致が発覚するリスクを内包します。このようなリスクを軽減するためには、段階的に開発を進めることが非常に有効です。具体的な方法として、次のようなことが挙げられます。このように、段階的に開発を進めることで、リスクを抑えつつ現場に適したシステムを構築できます。
小規模から始める
初期段階では、小規模なプロジェクトやプロトタイプを作成します。これにより、リスクを抑えつつ迅速なフィードバックを得られ、必要に応じて改善を行うことが可能です。特に、ノーコード・ローコードツールは、小規模な開発に適しており、短期間で結果を出せるようになります。
段階的に機能を追加する
最初は基本的な機能から始め、その後ユーザーからのフィードバックや業務ニーズに基づいて機能を追加していくことが効果的です。この方法では、ユーザーの実際の使用状況を観察しながら、必要な機能に優先順位をつけて追加できます。
テストと評価を実施する
各段階で開発した機能についてテストを行い、その結果を評価します。これにより、問題点や改善点を早期に発見し、次の開発サイクルに反映できます。特にノーコード・ローコードツールでは、迅速なテストと修正が可能です。
ユーザーからフィードバックを受ける
ユーザーからのフィードバックは、次の開発ステップで考慮すべき貴重な情報源となります。現場のニーズに合わせて柔軟に機能を追加・修正しながら、慎重に開発を進めましょう。
ローコード開発プラットフォーム上で稼働するPROACTIVE
SCSKが提供するAIネイティブERP「PROACTIVE」は、業務特化型・業界特化型のオファリングを通じて、企業の業務効率化と高度な経営判断を支援します。PROACTIVEは、ローコード開発基盤「ATWILL Platform」を基盤に、標準機能に加え柔軟なカスタマイズ機能を提供しています。
「ATWILL Platform」は、PROACTIVEの拡張性と柔軟性を支える基盤であり、開発者だけでなく非エンジニアも視覚的な操作でカスタマイズや機能拡張を行うことが可能です。
主な特徴は以下のとおりです。
柔軟な帳票作成機能
Excelフォーマットの取り込みにより、帳票の作成・編集が容易で、レイアウト変更にも迅速に対応できます。
多言語対応・ラベル名変更
画面表示の項目はログイン時の言語設定に応じて切り替わり、言語ごとに表示文言を管理できるため、多言語対応や独自用語の設定も容易です。
この基盤により、企業は業務特性や運用環境に合わせてPROACTIVEを自在にカスタマイズでき、システム変更時の開発コスト削減と高品質な対応を両立しています。
関連ページ
まとめ
ノーコード・ローコード開発は、プログラミングの知識が乏しい人でもシステムやアプリケーションを迅速に開発できる手法です。
- ・ ノーコード:コードの記述が不要でシンプルなアプリケーション開発に最適
- ・ ローコード:少量のコード記述で柔軟性と複雑な要件に対応可能
これらの手法は、開発スピードの向上やIT人材不足の解消、コスト削減など多くのメリットをもたらします。しかし、高度で複雑な要件には限界があり、セキュリティリスクへの対策も重要です。
この記事で紹介したように、ノーコード・ローコードは、コーディングの要否と柔軟性において、双方メリットとデメリットがあります。それぞれのメリットを活かし、目的や用途に合わせて活用することで、ビジネスの成長を強力に支援するツールとなるでしょう。