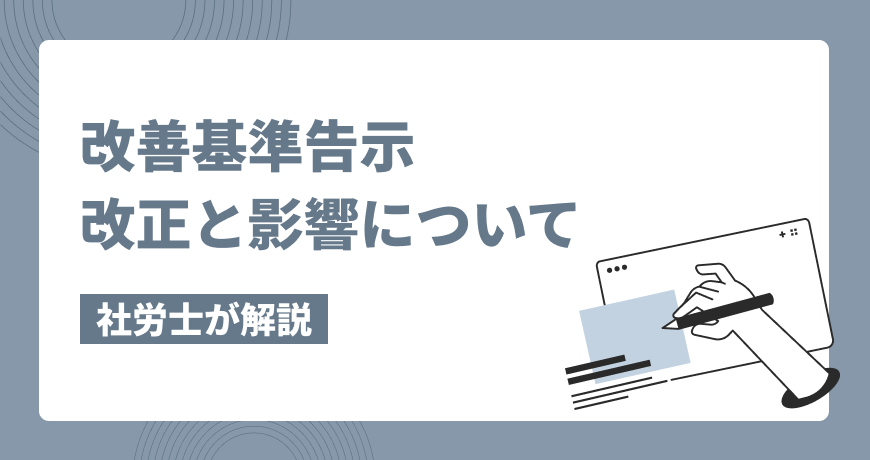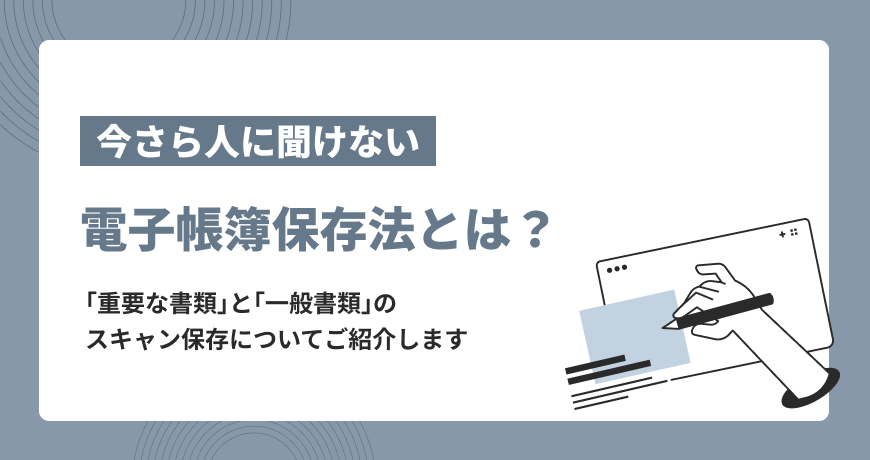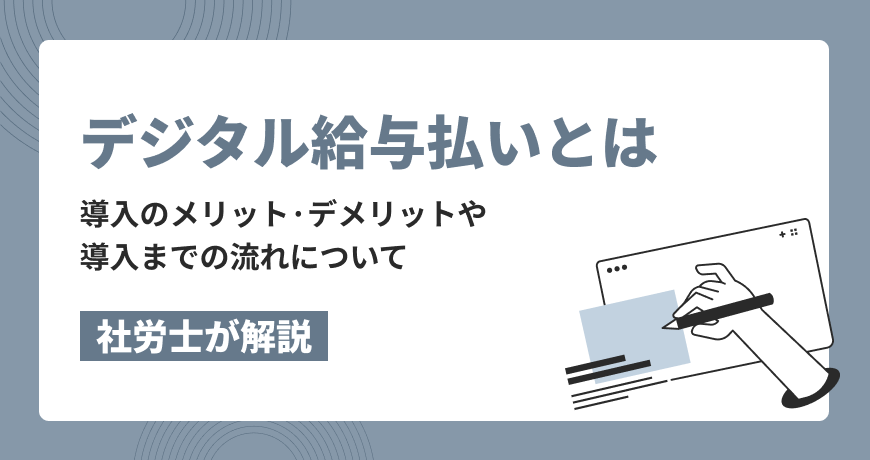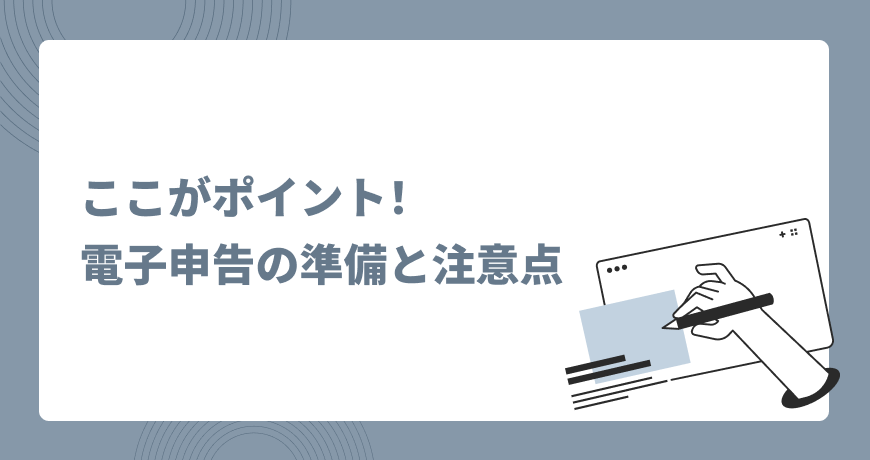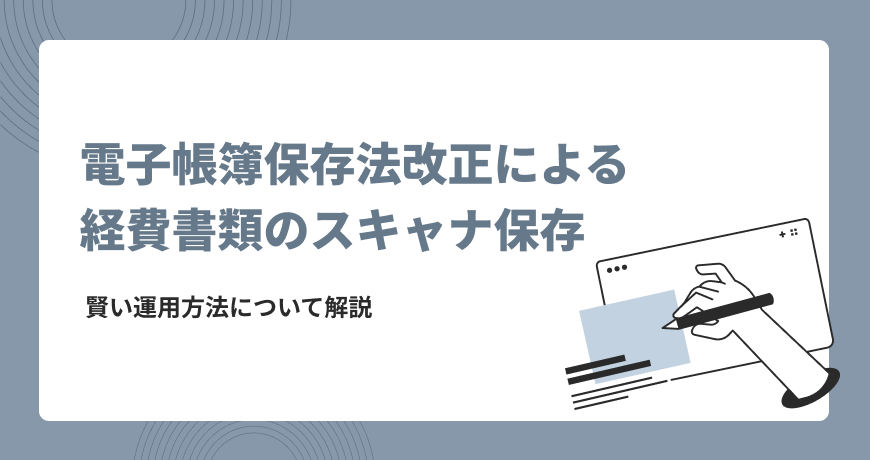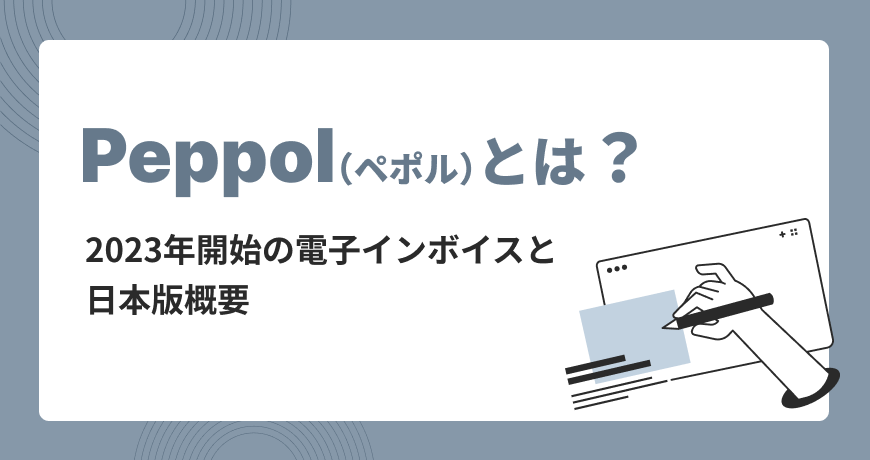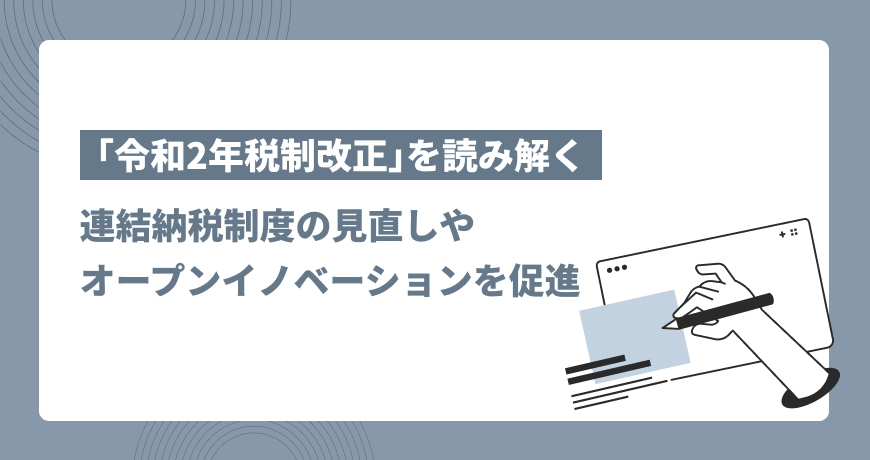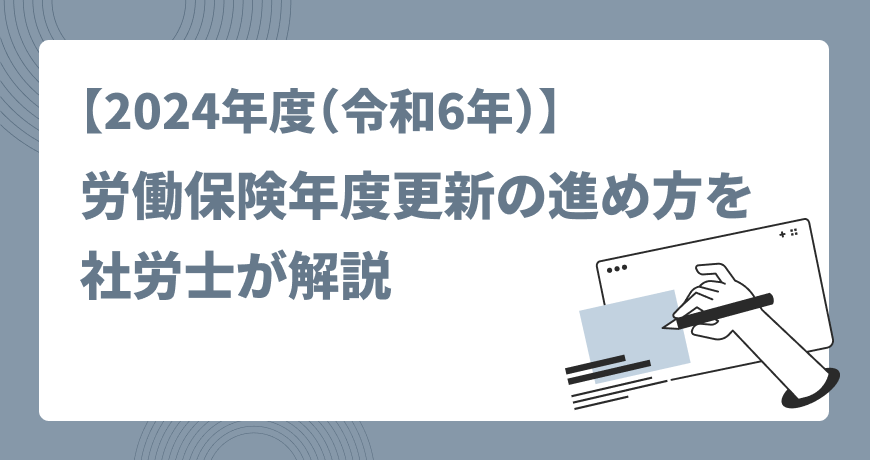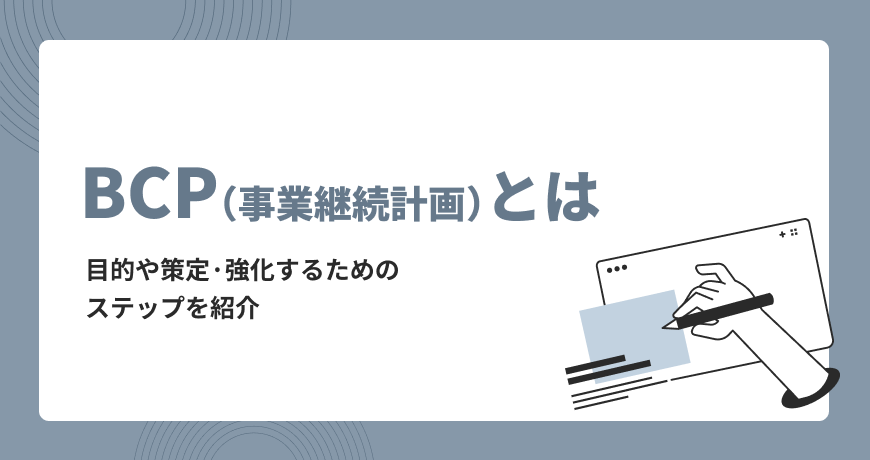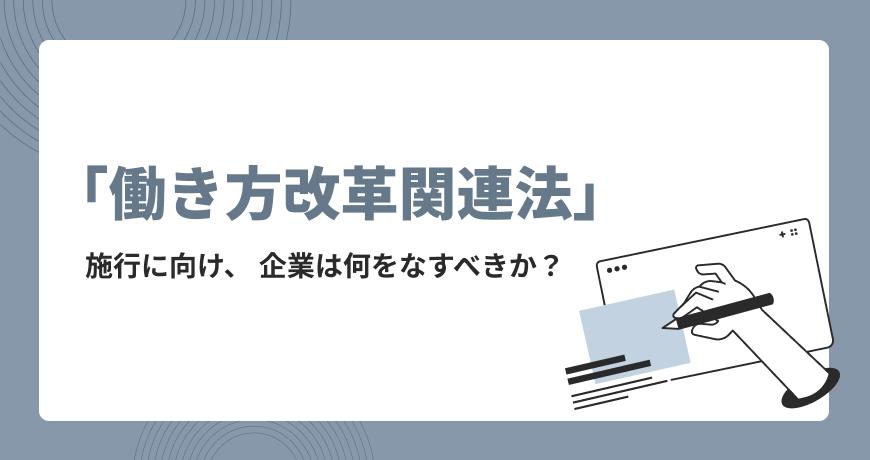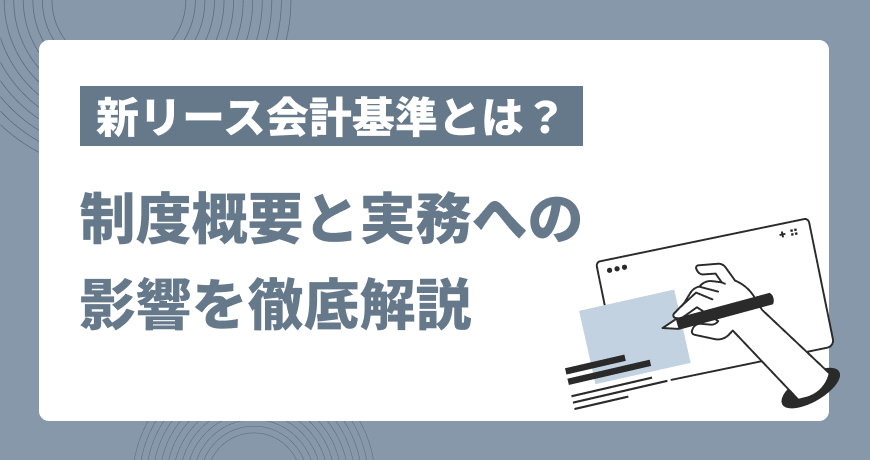
2024年9月13日に企業会計基準委員会(ASBJ)より「リースに関する会計基準」等(以下「新リース会計基準」という。)が公表されました。この基準は、2027年4月1日以降に開始する事業年度より強制適用となります。
新リース会計基準では、リースの定義の見直しが行われており、原則すべてのリース取引についてオンバランス化(貸借対照表に使用権資産およびリース負債を計上)する必要があります。
この記事では、新リース会計基準の適用に伴う、借手の財務や実務への影響について分かりやすく解説します。
新リース会計基準とは
新リース会計基準は2024年9月13日に企業会計基準委員会により、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」および企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」として公表されました。
新リース会計基準は、国際的な会計基準であるIFRS第16号「リース」との整合性や比較性のあるものにする取り組みの一環として整備されました。
主な改正内容として以下が挙げられます。
- • リースの定義・認識およびリース期間の見直し
- • 借手のリース取引区分の廃止と、リース取引のオンバランス化
- • 財務報告書における表示および開示内容の変更
適用時期
新リース会計基準は2027年4月1日以降に開始する連結会計年度および事業年度の期首より強制的に適用となります。なお、2025年4月1日以降に開始する連結会計年度および事業年度の期首からの早期適用も可能となっています。
3月期決算法人が、2027年4月より適用とした場合、この記事の掲載日(2025年7月)から約1年8か月後となり、対応の猶予はあまり残されていないのが現状となります。
対象企業
新リース会計基準が強制適用となる企業は以下の通りです。なお、下記以外の企業については任意での適用が可能です。
金融商品取引法の対象となる企業
金融商品取引法の対象となる上場企業およびその子会社・関連会社等が該当します。
会計監査人を設置する企業
会社法上の大法人等で会計監査人を設置している企業およびその子会社・関連会社等が該当します。
財務数値・財務指標への影響
新リース会計基準の適用により、すべてのリース取引は原則オンバランス化されます。具体的には、資産項目として「使用権資産」、負債項目として「リース負債」が計上されます。これらの数値が計上されることにより、借手企業の財務数値および財務指標には以下の影響が発生すると考えられます。
借手企業の財務数値への影響
| 財務諸表名 | 科目等 | 影響 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 貸借対照表 | 総資産 | ↑ | 使用権資産計上による増加 |
| 総負債 | ↑ | リース負債計上による増加 | |
| 損益計算書 | 営業費用 | ↓ | 支払リース料(営業費用)について、その一部が支払利息に計上 (営業外費用) |
| 営業外費用 | ↑ | ||
| キャッシュフロー計算書 | 営業CF | ↑ | 支払リース料(営業CF)について、その一部がリース負債の返済に充当(財務CF) |
| 財務CF | ↓ |
借手企業の財務指標への影響
| 財務指標 | 影響 | 概要 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | ↓ | 総負債の増加 |
| 総資産回転率 | ↓ | 総資産の増加 |
| ROA | ↓ | 総資産の増加 (ROA=利益÷総資産) |
| EBITDA | ↑ | 支払リース料について、使用権資産に係る減価償却費およびリース負債に係る支払利息として計上されるため、EBITDAの加算項目となる (EBITDA=税引前当期純利益+支払利息+減価償却費) |
リースの適用範囲・識別・期間
新リース会計基準では、リースの適用範囲や識別基準が変更となっています。
リースの適用範囲
新リース会計基準は、契約の名称などに関わらず、以下を除いてすべてのリースが対象となります。
- • 実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」の範囲に含まれる運営権者による公共施設等運営権の取得
- • 鉱物、石油、天然ガスおよび類似の非再生型資源の探査をする権利または使用する権利の取得
- • 収益認識会計基準の範囲に含まれる貸手による知的財産のライセンスの供与
リースの識別
従来のリース会計基準では、リースはファイナンス・リースまたはオペレーティング・リースに分類されていました。ファイナンス・リースの判定基準としては、
- • 解約不能(ノンキャンセラブル)
- • フルペイアウト(リース料総額の現在価値が見積購入金額の概ね90%以上または解約不能のリース期間がリース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上であること)
が採用されていました。
一方、新リース会計基準では、以下の2つの要件を満たすかどうかで識別します。
| 要件① | 概要 |
|---|---|
| 資産が特定されているか | 契約書等により資産が特定・明記されており、サプライヤーが実質的な代替権を有していないこと |
| 要件② | 種類 | 概要 |
|---|---|---|
| 資産の使用を支配する権利があるか | 経済的利益 | 使用期間全体を通じて特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受できる権利を有する |
| 指図権 | 資産の使用方法を指図する権利を有している | |
| 顧客のみが資産を稼働する権利を有している | ||
| 顧客が資産の使用方法について事前に設計・決定している |
従来のリース会計基準とは異なり、契約の法形式による判定ではなく、経済的な実態に基づいて判定が必要となります。リース契約書による確認のみならず、他社の資産を利用しているかなど現場へのヒアリング等による調査を踏まえての判定が必要となります。
リースの期間
従来のリース会計基準では、リース期間はリース契約に定められている解約不能期間とされていました。新リース会計基準では、解約不能期間に、以下を考慮した期間をリース期間と定めています。
- • 借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間
- • 借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間
なお、「合理的に確実」の判断は、経済的インセンティブを生じさせる要因を考慮して決定することとなります。
- • 延長または解約オプションの対象期間に係る契約条件(リース料、違約金、残価保証、購入オプションなど)
- • 大幅な賃借設備の改良の有無
- • リースの解約に関連して生じるコスト
- • 企業の事業内容に照らした原資産の重要性
- • 延長または解約オプションの行使条件
リース資産ごとにリース期間の検討が生じるため、早期の調査・準備が必要となります。
借手の会計処理
新リース会計基準の下での借手の会計処理は以下となります。
仕訳概要
リース取引における会計処理は、取引開始時に使用権資産およびリース負債の計上、リース料支払時の処理、使用権資産の償却が行われます。各勘定科目の金額算定方法は後述します。
リース開始時
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 使用権資産 | XXXX | リース負債 | XXXX |
リース料支払時
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース負債 | XXXX | 現金預金 | XXXX |
| 支払利息 | XXXX | ||
使用権資産の償却
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | XXXX | 使用権資産 | XXXX |
借手のリース料
借手は、リース開始日において、その時点における未払の「借手のリース料」の割引現在価値をリース負債として計上します。「借手のリース料」とは、借手が借手のリース期間中に原資産を使用する権利について、貸手に対して支払う対価になります。「借手のリース料」は以下の方法で算定されます。
リースとサービスの配分
リース契約における対価額を、リースを構成する部分とリースを構成しない部分(サービス)に配分します。配分は、リースの独立価格とサービスの独立価格の比率により行います。
(前提条件)
- • 契約における対価の額の総額:50,000千円
- • リースを構成する部分の独立価格:37,800千円
- • リースを構成しない部分の独立価格:16,200千円
(独立価格の比率)
- • 独立価格の合計額:54,000千円
- • リースを構成する部分の独立価格の比率:0.7(37,800÷54,000)
- • リースを構成しない部分の独立価格の比率:0.3(16,200÷54,000)
(リースとサービスの配分額)
- • リースを構成する部分の配分額:35,000千円(50,000×0.7)
- • リースを構成しない部分の配分額:15,000千円(50,000×0.3)
リース料の構成要素
リース料は以下の要素により構成され、これらの割引現在価値をリース負債として計上します。
- • 借手の固定リース料
- • 指数またはレートに応じて決まる借手の変動リース料
- • 残価保証に係る借手による支払見込額(※)
- • 借手が行使することが合理的に確実である購入オプションの行使価額
- • リースの解約に対する違約金の借手による支払額
(※)従来のリース会計基準では、契約上定められていた残価保証額が計上されていましたが、新リース会計基準では、残価保証額に係る借手による支払見込額(残価保証額から原資産の見込残存価額を控除したもの)が計上されることとなります。
使用権資産およびリース負債の当初測定
使用権資産およびリース負債の当初測定は、まずリース負債を測定し、その後に使用権資産を測定します。
リース負債の当初測定
借手は、リース負債の計上額の算定にあたって、リース開始日における未払の「借手のリース料」から、これに含まれている利息相当額を合理的な見積額を控除した割引現在価値により算定します。
(前提条件)
- • 借手のリース期間:3年
- • 借手のリース料:年額10,000千円
- • 現在価値の算定に用いる割引率:5%
(リース負債の当初測定)
- • 1年目リース料の現在価値:10,000÷(1 + 0.05) = 9,524
- • 2年目リース料の現在価値:10,000÷(1 + 0.05)2 = 9,070
- • 3年目リース料の現在価値:10,000÷(1 + 0.05)3 = 8,638
- • リース負債の当初測定額:27,232千円
使用権資産の当初測定
使用権資産は、先に算定した「リース負債の当初測定額」に以下の内容を加減した額となります。
- • (+)リース開始日までに支払ったリース料
- • (+)付随費用
- • (+)借地権の設定に係る権利金等
- • (+)資産除去債務
- • (+)建設協力金等の差し入れ預託保証額の一部
- • (-)リース・インセンティブ
(前提条件)
- • 借手のリース期間:3年
- • リース負債の当初測定額:27,232千円
- • 資産除去債務の見積額:1,200千円
- • 現在価値の算定に用いる割引率:5%
(使用権資産の当初測定額)
- • 資産除去債務の割引現在価値:1,200÷(1 + 0.05)3 = 1,036
- • 使用権資産の当初測定額:28,268千円
短期リースと少額リースの簡便的な取り扱い
新リース会計基準においても短期リースと少額リースについてはオンバランス化せずに、借手のリース料をリース期間にわたって定額法にて費用計上することが可能です。
短期リース
短期リースは、リース開始日において借手のリース期間が12か月以内であり、購入オプションを含まないリースになります。
少額リース
少額リースは、以下にいずれかに該当するものとなります。
- • 重要性の乏しいリースで、かつ、リース契約1件あたりのリース料の総額が300万円以下
- • 新品時の原資産の価額が少額であるリース(5千米ドル以下)
新リース会計基準による実務への影響
新リース会計基準の適用にあたり、実務へは以下のような影響があると考えられます。
不動産賃貸借契約のオンバランス処理
新リース会計基準では、すべてのリース取引についてオンバランスすることを原則としています。とりわけ、不動産賃貸借契約は、従来の基準ではオペレーティング・リース取引に分類されていましたが、新リース会計基準では、その不動産が「特定」されており、かつ、「支配」している状態である場合は、オンバランスする必要があります。
また、リース期間も、不動産賃貸借契約で定められている期間ではなく、その不動産を使用する予定の期間となるため、十数年など長い期間になることが想定されます。
そのため、オンバランスされる金額が多額となり、財務数値・財務指標への影響が懸念されます。
リース対象範囲の拡大
従来の基準では、リース契約書の内容を基に、ファイナンス・リースに該当するか否かの判定を実施していましたが、新リース会計基準では、原資産が「特定」されており、かつ、「支配」している状態である場合は、リース取引に該当しオンバランスとする必要があります。
そのため、「リース契約書」以外の契約でも「リース取引」に該当するものが生じる可能性があります(いわゆる隠れリース)。具体的には以下のようなものが該当する可能性があります。
- • 看板、テナント契約
- • 専用金型による外注加工取引
- • 倉庫、車両運搬具、工場設備
- • サーバ、クラウドサービス
これらは、契約書等の書面調査のみならず、実態調査を踏まえて判断を行う必要があるため、情報収集や判断に時間がかかることが想定されます。
借手のリース期間の算定
新リース会計基準におけるリース期間は、解約不能期間に加え、延長または解約オプションの対象期間を含めた期間となります。この際、オプションの行使について「合理的に確実」の判断する必要がありますが、その判断には経済的インセンティブなどの要因の考慮することが求められます。
とりわけ不動産に関しては、その用途や事業計画、設備投資の状況などを総合的に検討する必要があります。また、不動産の管理部門と経理部門が異なっているケースも想定されるため、部署間の情報共有や意思決定に時間を要する可能性があります。
新リース会計基準対応も万全!Fit to Standardなシステム刷新ならPROACTIVE
AIネイティブな次世代ERP「PROACTIVE」は、30年以上の歴史をもつ国産ERPとして、日本の商習慣に即した形で会計領域における業務機能を標準で網羅しており、周辺ソリューションとも柔軟に連携可能なため、Fit to Standardで導入・運用していただけます。
また、SaaS型にてご提供しており、導入後も継続的にアップグレードを行っております。
新リース会計対応をはじめ、法改正への対応やセキュリティ機能の強化については、四半期に一度のペースでアップデートを実施しています。
そのため、お客様は法改正に伴うシステムの更新にかかる手間やコストを気にすることなく、常に最新の機能をご利用いただけます。
関連ページ
- ニュース「PROACTIVE」は新リース会計基準に対応します!(4/10)
- リース資産管理システム・機能
- 会計の業務改善/オファリング
- Fit to Standard
- ERP活用におけるFit to Standardとは:必要性やメリット、進め方を解説
まとめ
新リース会計基準の適用にあたっては、借手企業において、リース契約に関する情報収集、会計方針の検討、リースの識別および金額の算定、システム対応、データ移行など、さまざまな対応が求められます。
加えて、財務数値や財務指標にも多大な影響が生じることから、経営管理、業務プロセス、内部統制を含めた全社的かつ包括的な対応が必要となるでしょう。